1979年に発表されたPink Floyd「Another Brick in the Wall, Part 2」は、ただの反抗的なロックソングではありません。
それは、子供たちの合唱とファンキーなギターリフに乗せて、「教育とは何か」「個人の自由とは何か」という問いを静かに、しかし鋭く投げかける曲です。
アルバム『The Wall』の中で描かれるのは、主人公が心に積み重ねていく“見えない壁”。
その壁を形作る「レンガ」は、社会から受けた傷や抑圧、そしていつのまにか内側に生まれた恐れの象徴でもあります。
なぜ、このシンプルなフレーズが、世界中の若者の心に火をつけたのでしょうか。
なぜ、子供たちの無垢な声が、権力への抗いの象徴となりえたのでしょうか。

おとはじ
今日は、その「壁のレンガ」が語る、静かなる反抗の意味を、音楽的構造と時代背景からひもといていきます。
🎸 洋楽の「あのフレーズ」深掘りコラム【Vol. 15】
Pink Floyd「Another Brick in the Wall, Part 2」の「壁のレンガ」が象徴する、静かなる反抗
1979年にリリースされたPink Floydの「Another Brick in the Wall, Part 2」。 プログレッシブ・ロックの金字塔であるコンセプト・アルバム『The Wall』からのシングルカットでありながら、ディスコビートを取り入れたファンキーなギターリフと、子供たちの合唱という斬新なアイデアで、世界的な大ヒットを記録しました。
この曲のシンプルで反復的なフレーズは、なぜこれほどまでに人々の心を捉え、教育制度への静かなる反抗のシンボルとなったのでしょうか?今日は、この「壁のレンガ」に隠された、軽やかで、深い秘密を掘り下げてみましょう。
🎼 今日の深掘りフレーズ
|
アーティスト
|
曲名
|
フレーズの場所
|
フレーズの正体
|
|
Pink Floyd
|
Another Brick in the Wall, Part 2
|
楽曲全体
|
Dドリアン・モードによるファンキーなギターリフ
|
🎵 軽やかな考察:なぜこのフレーズは「反抗のアンセム」となったのか?
1. 音楽的構造:ディスコとプログレの融合
この曲のフレーズは、一見シンプルながら、非常に巧妙な音楽的構造を持っています。
•Dドリアン・モード: リフは、Dドリアン・モードという、マイナー(短調)でありながら少し明るい響きを持つ音階で構成されています。これにより、曲全体にクールで洗練された雰囲気と、どこか物悲しい浮遊感が生まれています。
•ファンク・グルーヴ: ギタリストのデヴィッド・ギルモアは、ディスコミュージックから影響を受け、16分音符を基調としたカッティング(歯切れの良いリズムギター)を導入しました。このファンキーなグルーヴが、プログレッシブ・ロックの難解さを払拭し、曲に抗いがたいダンスのリズムを与えています。
•シンプルなコード進行: 曲の大部分はDm(Dマイナー)のコード一発で進行します。このシンプルさが、リフの反復性と歌詞のメッセージを際立たせています。
2. 文化的背景:教育への痛烈な批判
この曲は、その歌詞とコンセプトで、社会に大きな議論を巻き起こしました。
•「壁」の意味: アルバム『The Wall』は、主人公ピンクが、社会や人間関係から自らを隔離する「壁」を築いていく物語です。「Another Brick in the Wall(壁の中のもう一つのレンガ)」とは、その壁を構成するトラウマの一つを象徴しています。
•教育への批判: 「We don’t need no education / We don’t need no thought control」(教育なんていらない/思考のコントロールなんていらない)という歌詞は、当時の画一的で抑圧的なイギリスの教育制度に対する痛烈な批判です。子供たちの合唱がこのメッセージを歌うことで、その説得力とインパクトは絶大なものとなりました。
•放送禁止: この曲は、イギリス国内での議論を巻き起こしただけでなく、南アフリカでは学生デモの象徴として歌われた結果、政府によって放送禁止にされました。 しかし、この禁止措置はかえって曲のメッセージ性を強め、「反抗のシンボル」として世界的な共感を呼ぶことになります。
3. 弾き語りへの応用:カッティングのリズム
このリフは、ギターの弾き方としては、リズムが重要になります。
•弾き方のヒント: 複雑なコードは出てきませんが、右手の16分音符の正確なカッティングが、この曲のファンキーなグルーヴを生み出す鍵です。手首のスナップを効かせ、歯切れの良いサウンドを目指しましょう。
💡 今日の音楽豆知識
この曲の子供のコーラスは、ロンドンのイズリントン・グリーン・スクールの生徒たちによって録音されました。
当時、学校にはレコーディング参加に対して少額の報酬のみが支払われ、生徒たちには印税(ロイヤリティ)は支払われていませんでした。
その後、曲の大ヒットにより問題が注目され、音楽家の権利管理団体(PPL)が「放送使用料に応じた支払い」を申請。
最終的に、生徒たちには 追加の支払いが行われることになりました。
子供たちの声が、音楽史に残る「反抗のアンセム」の象徴となった瞬間です。
次回は、また別の名曲の「あのフレーズ」を深掘りします。お楽しみに!

おとはじ
取り上げて欲しい洋楽(フレーズ)があればコメント下さいね!
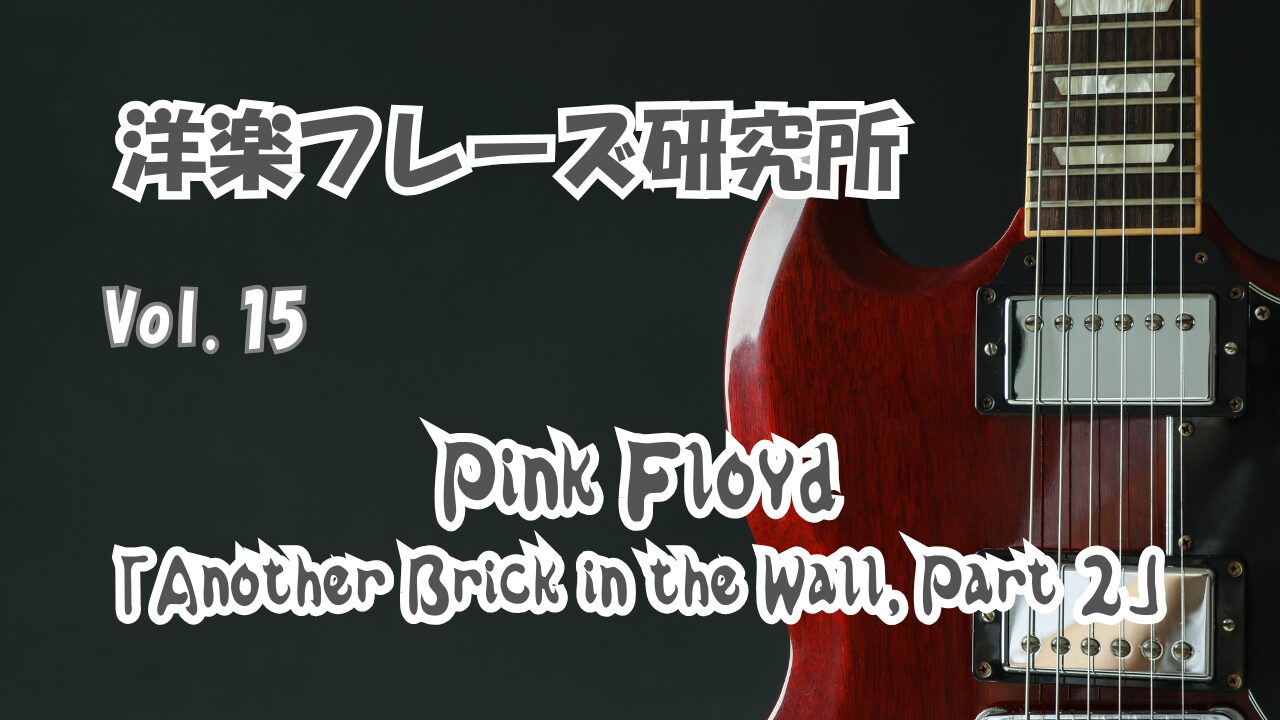
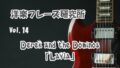
コメント