あなたの卒業アルバム、どこにありますか?
本棚の奥、実家の引き出し、あるいはスマホの写真フォルダ?
久しぶりに開いて、懐かしい顔や寄せ書きに目を細めた記憶がある人も多いはずです。
でも今、そんな“あたりまえの思い出”が、なくなろうとしています。
SNS全盛の現代、卒アルは「危険なもの」になってしまったのでしょうか。
それとも、私たちが“記憶の残し方”を見直すべき時が来ているのでしょうか。
いま一度、卒アルの未来について、一緒に考えてみませんか?
「当たり前」が失われる時代に
卒業式のあと、最後に渡される卒業アルバム。
クラスの集合写真、部活仲間との笑顔、担任の先生のコメント。
それは単なる記録ではなく、「あの頃の自分」と再会できる“心のアルバム”です。
けれど今、この「当たり前」の存在が、静かに姿を消し始めています。
子どもたちにとって、かけがえのない“思い出の象徴”であったはずの卒業アルバム。
その未来が、いま大きく揺らいでいるのです。
▶ 参考リンク:卒業アルバム、存続の危機に…AI画像悪用やサイバー攻撃が背景(Yahoo!ニュース)
なぜ卒業アルバムが消えようとしているのか?
背景1:AIによる画像悪用が現実に
2024年から2025年にかけて、全国各地で起きたショッキングなニュース。
卒業アルバムに掲載された生徒の写真が、AIによって性的な画像に加工され、SNSで拡散されていたというのです。
このAIポルノ被害は、もはやフィクションでも都市伝説でもなく、現実の子どもたち、そして保護者を深く傷つける事件へと発展しました。
「誰にも見せたくない自分の写真が、知らないうちに“晒し者”になっていた」
そんな言葉にならない恐怖が、保護者たちの間で広がっています。
背景2:サイバー攻撃による情報流出
さらに、卒アル制作会社がサイバー攻撃を受け、個人情報が流出したという事例も複数発生。
名前、顔写真、学校名、生年月日などが第三者の手に渡ることで、なりすましや詐欺、ストーカー被害への懸念も高まっています。
「卒アルは、もう安全なものではないのかもしれない」
そんな不安が現実味を帯びて、教育現場にも重くのしかかっているのです。
背景3:教員と業界の“限界”
卒業アルバムの制作は、単に写真を集めて冊子にするだけの作業ではありません。
教員は以下のような業務をこなしています。
• 写真選定とチェック
• レイアウト確認・コメント回収
• 制作会社とのやり取り・校正対応
多忙な教育現場にとって、この作業量は非常に重く、教員の残業や休日出勤の原因にもなっていると指摘されています。
一方、写真スタジオ側も人手不足や経営難に直面。
特に地方の中小業者では対応が追いつかず、制作自体を断念せざるを得ない学校も出てきているのです。
それでも「卒アルは残したい」と願う保護者は多い

では、人々は本当に卒業アルバムを「不要」と感じているのでしょうか?
複数の調査によれば、6〜8割の保護者が「卒アルは残したい」と考えていることがわかっています。
たとえば、ある調査では67.3%の保護者が「子どもの卒アルは大切な思い出になる」と回答し、
また別の調査では、保護者や高校生の約8割が「紙で残したい」と希望しているという結果も出ています。
一方で「なくなってもよい」と答えた人はごくわずかにとどまり、多くの家庭が“思い出のかたち”としての卒アルに、今なお価値を感じていることがうかがえます。
🔗 出典リンク:卒業アルバムは必要?保護者と高校生の本音(exciteニュース)
卒アルは、過去の遺物ではない。「未来に残したい記憶のメディア」
なぜ、卒業アルバムは人々の心を惹きつけ続けるのでしょうか?
• デジタルに埋もれない、“モノ”としての温かさがある
• 親から子へ、友から友へ、語られるきっかけになる
「本棚から引っ張り出して見返す卒アルのほうが、スマホのフォルダよりも泣ける」
そんな声にうなずく人も多いのではないでしょうか。
そして何より、「あの1冊があったから、今も友達とつながっていられる」という人間関係の“原点”がそこに詰まっています。
解決のカギは、“進化”にあり
私たちは今、「残すか/捨てるか」ではなく、「どう進化させるか」という選択肢の前に立たされています。
✅ AIで制作の効率化と安全性を両立
全国3000校以上でAI活用が始まり、制作の効率化とリスク軽減の両立が進んでいます。
✅ 児童・生徒が“つくり手”になる卒アル教育
ある小学校では、卒アルの編集を子どもたち自身が担っています。
こうして卒アルは、「与えられるもの」から「学びを通して生まれる記憶の集積」へと変化。
卒業式の日、「これ、自分で作ったアルバムなんだ」と語る子どもたちの誇らしげな表情が、何よりの答えかもしれません。
【提案】“残したい気持ち”を起点に考える
「リスクがあるからやめよう」ではなく、
「残したいから、どう安全に、どう心に届くかたちにするか」を考えていく。
そのために今後、以下のような工夫も必要でしょう。
• 希望者のみ紙媒体を発行
• デジタル版は顔認識でログイン制限
• 自宅で自分のページだけ印刷できるオンデマンド方式
• オンラインでコメント投稿
• 保護者が「思い出の一言」を添えられる機能
• 家族アルバムとの連携
「卒アル=学校が作るもの」という発想を超えて、「子どもの記憶を、家族みんなで共有できるメディア」へと発展させるチャンスです。
私自身の記憶から見えた“卒アルの変化”
私が子どもだった頃、卒業アルバムは当然のように存在していました。
今でも大切に保管してありますが、頻繁に見ることはありません。
それでも、ふとした時に開いてみると、懐かしい友だちの顔や、あの頃の空気がよみがえってきます。
驚くべきことに、その巻末には生徒一人ひとりの住所や電話番号など、個人情報が一覧で記載されているページがあるのです。
今では考えられないことですが、当時はそれが“あたりまえ”でした。
そして時代が変わり、私の息子や娘の世代になると、アルバムの形式も少しずつ変化していきました。
紙のアルバム自体は今も手元にありますが、個人情報は一切載らなくなり、掲載されなかった写真やスナップはデータで配布されるようになりました。
便利になった反面、その“デジタルの手軽さ”を悪用されるリスクも現実になっています。
どこかにアップされた画像が加工され、意図しない形で拡散されてしまう…。
それは子どもたちにとっても、家族にとっても、非常に悲しく、つらい出来事です。
“残したい”という気持ちと、“守らなければ”という責任——
私自身、親として、その狭間で揺れ動く感情を何度も経験してきました。
【まとめ】卒業アルバム、それは“心をつなぐ記憶装置”
卒業アルバムを取り巻く環境は、今、確かに逆風の中にあります。
けれどそれでも、人は“記憶をかたちに残したい”と願うものです。
ページをめくったときに感じる、あたたかい気持ち。
忘れていた誰かの笑顔や、もう会えない先生の言葉に再び出会える瞬間。
それは、スマホのアルバムやSNSの投稿にはない、かけがえのない体験です。
だからこそ、「もういらない」と切り捨てるのではなく、時代に合わせて進化させ、“残したくなる卒アル”へと育てていくことが大切なのではないでしょうか。
いま、子どもたちの未来に本当に必要なのは、「ただの記録」ではなく、「自分自身の記憶に誇りを持てる記録」。
そして私たち大人には、その“記憶の器”をどう守り、どう作っていくかを考える責任があります。
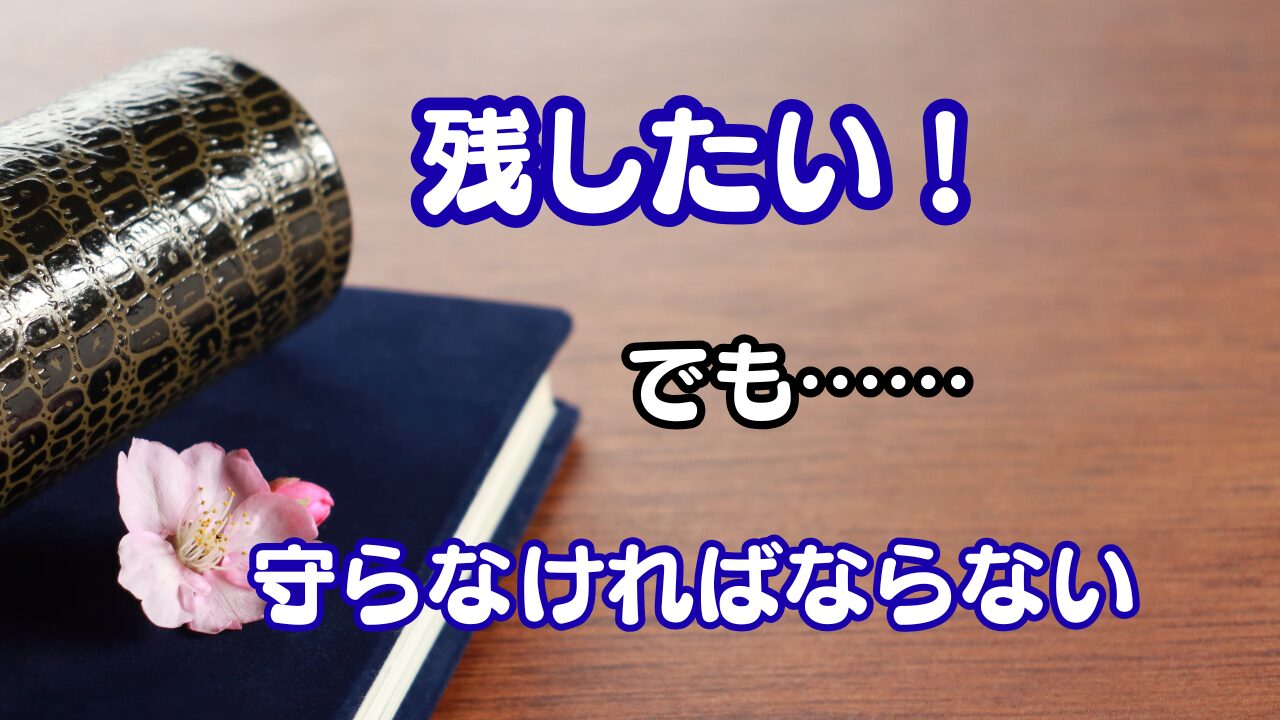


コメント