夏祭りの屋台でおなじみの「お好み焼き」「焼きそば」「たこ焼き」。庶民の味として長年親しまれてきた“粉もん文化”ですが、いま大きな転換期を迎えています。帝国データバンクの調査によると、2025年1~7月に全国で倒産した「お好み焼き・焼きそば・たこ焼店」は17件(前年同期比30.7%増)にのぼり、過去15年で最多のペース。特に大阪では6件と突出しており、競争の激化や物価高、人件費の上昇が経営を直撃しているのが現状です。
では、倒産した店舗は一体どこなのか──。観光需要やインバウンドの追い風がある一方で、小規模店を中心に苦境に追い込まれる「粉もん業界」の実態に迫ります。
出典:「粉もん」の倒産が過去15年間で最多ペース(東京商工リサーチ|Yahoo!ニュース)
倒産した店舗名は現時点では公表されていない

今回のニュースで取り上げられているのは、「お好み焼き・焼きそば・たこ焼店」という業種全体の倒産件数や原因です。そのため、どのお店が倒産したのかという具体的な店名までは発表されていません。
調査を行ったのは信用調査会社で、公式にまとめられる内容は「件数」「地域」「原因」などの統計データが中心です。店名や所在地のような詳細は、専門の報告書や業界向け資料に含まれることはあっても、一般に公開されることはあまりありません。
「どのお店だったのだろう?」と気になる方も多いと思いますが、現時点では公表されていない以上、確認することはできません。記事で紹介されているデータは、あくまで“業界全体の動き”を知るためのものだと受け止めていただければと思います。
インバウンド需要が増えても倒産が増える理由
インバウンド需要が拡大すれば本来は売上が伸びるはずですが、実際には「粉もん」店の倒産は過去最多ペースで増えています。その背景には、次のような要因があります。
店舗数が多いため、外国人観光客の増加があっても売上増加は一部の有名店に集中し、その他の店舗には十分に波及していません。
・小規模店の集客力不足
小・零細規模の店は、外国人客を意識した味の工夫や店舗改装、SNS発信といった集客ノウハウに乏しく、インバウンド需要を取り込みきれていません。
・物価高・人件費高騰
小麦粉や油、ソースなど主要食材の値上がりに加え、人件費や光熱費も上昇。売上が伸びてもコストが膨らみ、利益が追いつかない状況に陥っています。
・価格転嫁の難しさ
「庶民の味」として親しまれる粉もんは値上げがしにくく、価格を上げれば客足の減少に直結します。そのため、コスト増を十分に転嫁できず、経営難が深刻化しています。
つまり、観光客や外国人が増えても、すべての店舗が恩恵を受けられるわけではありません。売上増加よりもコスト上昇や競争激化の影響が大きく、多くの店が厳しい経営状況に追い込まれているのが現実です。
大阪における粉もん店舗の競争構図
大阪は粉もんの店舗数が全国でも突出して多く、その結果、日常的に激しい競争が起きています。店舗数が多いほど売上の分散が進み、資金力や集客力の乏しい小規模店は生き残りが難しくなります。
観光客の増加という追い風はありますが、恩恵を受けられるのは一部の有名店や立地に恵まれた店舗に限られ、すべての店が潤うわけではありません。そのため、市場全体では二極化や淘汰が進み、店舗数の多さ自体が倒産増加の背景となっているのです。
以下は主要都道府県の粉もん(お好み焼き・焼きそば・たこ焼店)店舗数と、人口10万人あたりの店舗数を比較した表です。
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口10万人あたり店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 1,656 | 58.45 |
| 2 | 兵庫県 | 1,947 | 35.14 |
| 3 | 大阪府 | 2,850 | 32.25 |
| 4 | 徳島県 | 232 | 30.37 |
| 5 | 高知県 | 210 | 28.46 |
| 6 | 京都府 | 666 | 25.35 |
| 7 | 香川県 | 235 | 24.83 |
| 8 | 岡山県 | 548 | 27.02 |
| 9 | 奈良県 | 322 | 23.40 |
| 10 | 愛媛県 | 254 | 19.56 |
| – | 東京都 | 1,215 | 9.07 |
この表から、店舗数・人口比ともに広島・関西圏が圧倒的に多いことが分かります。
【参考資料】👉– ねとらぼリサーチ「都道府県別『お好み焼き屋』店舗数ランキング①(2021年版)」(ITmedia)👉– 都道府県別「お好み焼き・たこ焼き店」店舗数ランキング(都道府県別統計とランキングで見る県民性)
大阪は「販売不振型」、広島は「静かな閉店型」

ここで注目すべきは広島です。人口比では全国トップを誇りますが、では倒産の現状はどうなっているのでしょうか?
同じ「粉もん文化」の代表地でも、大阪と広島では倒産や閉店の様相が大きく異なります。
大阪の場合
大阪は店舗数が全国でも突出して多く、競争の激化による販売不振型の倒産が目立ちます。帝国データバンクの2025年上半期集計でも、大阪は全国最多の倒産件数を記録しており、負債1,000万円以上の法的整理に追い込まれる店舗が多いのが特徴です。物価高や人件費高騰も重なり、小規模店が次々に経営難に陥っています。
広島の場合
一方、広島は人口比で全国一の「粉もん王国」でありながら、統計上の倒産件数は目立ちません。これは、販売不振による法的整理よりも、高齢化や後継者不足、物価高騰などを背景とした自主的な閉店・廃業が多いためです。広島市内の老舗や個人経営の店を中心に「静かに暖簾を下ろす」ケースが広がっており、倒産統計には反映されにくい実態があります。
まとめ
- 大阪:競争激化による「販売不振型」の倒産が中心
- 広島:法的倒産は少ないが「静かな閉店型」の廃業が拡大
両地域ともに「粉もん文化」を象徴していますが、その経営課題や倒産・閉店の形は大きく異なっているのです。
今後の粉もん文化と課題
庶民の味として長年親しまれてきた「粉もん」ですが、いまや観光需要の追い風だけでは経営を支えきれない現実が浮き彫りになっています。大阪では競争激化とコスト増による「販売不振型」の倒産が進み、広島では統計に表れにくい「静かな閉店型」の廃業が広がっています。
今後、粉もん文化を守り続けるためには、単に価格を上げるのではなく、魅力的な商品開発やSNSを活用した情報発信、インバウンド客への対応力強化など、時代に合わせた工夫が求められます。また、後継者不足や高齢化といった構造的な課題にも正面から向き合う必要があるでしょう。
「粉もん」は日本人にとってのソウルフードであり、観光客にとっても日本の食文化を体験する入口です。厳しい経営環境の中でも、この文化をどう未来につないでいくのか…。それが今、問われています。


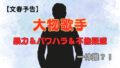
コメント